俺達の関係は中学生でも、高校生でもない。
その中間にあたる、中途半端な時期。
中学を卒業し、高校入学を控えた春休みから始まった。
ネネちゃんが俺の家に遊びにきて、卒業祝いを強請った。
中学なんて義務教育なんだから、誰だって卒業できるんだぞ。
なんて言ったら、
じゃあ高校の合格祝いでいいわよ。
なんて言うんだ。
いや、それならネネちゃんと同じく無事高校進級が決まっている俺も貰って然るべきなんだけど。
って言ったら、
「うん、だからあげる。ネネのハジメテ。」
予想外すぎて理解できなかった。
『ハジメテ』?
そんな意味ありげに言われたら、思春期の俺としてはソッチ方面にしか解釈できないんですけど。
「だからネネにはしんちゃんのハジメテ頂戴?」
「え?えっと、ちょっと待とうか。ハジメテって…?」
気付けば、俺とネネちゃんの距離は縮まっていた。
俺の後ろにはベッド。
前には上目づかいでにじり寄ってくるネネちゃん。
身動きが取れなくて、焦る俺。
そんな、今まで味わったことのないような空間を作り上げる目の前の彼女は、当然だとでも言うように、言い放った。
「だから、えっちしよ?」
眩暈がしそうだった。
いや、実際クラっとした。
左手で目を覆ったら、後頭部からベッドに倒れこんでしまった。
今俺は、天井を仰ぎ見るような体勢だ。
ネネちゃん。
あなた彼氏いるでしょ?
俺の当然の言葉は空を切る。
自分の部屋の天井を見ながら、ネネちゃんが何を意図しているのか思いを巡らせようとした。
が、すぐにそれは中断させられた。
「しーんちゃん。ゴムならネネが持ってるよ?
他に何か心配事でもあるの?」
俺の視界、天井を遮ったのは可愛い少女の顔。
頬をくすぐる、長くてさらさらとした茶色い髪の毛。
それに加えられた、似つかわしくない言葉。
「彼氏がいる人に迫られても、俺困るぞ…。」
少しでも動いたら、動かれたらキスをしてしまいそうな距離だったので、
とりあえず彼女の両頬を両手で押さえた。
何も問題が解決しないまま、流れに身を任せるなんてできない。
…でも、彼女の両頬を押さえたのは失敗だった。
俺の手が、このまま彼女の顔を自分の顔に近づけたくなってしまったから。
「彼氏?そんなの気にしなくていいのよ。
ネネ、ハジメテはしんちゃんと、って前から決めてたもん。」
いや、意味が分からないんですけど。
俺の体目当てなの!?
「彼氏と彼女になったらいつかは別れちゃうでしょ?
でも友達のままなら、余計な感情をはさまなくていいから、一生モノじゃない?
ネネはしんちゃんのこと大好きだから、ずっと一緒に居たい。」
何それ!?
所謂セフレ宣言ですか!?!?
「ネネのこと好きにしていいのはしんちゃんだけだよ?」
いやいや、そんな殺し文句イタイケな少女が口にしていい言葉じゃないから!!
思春期の少年には爆弾だからね!!
俺の理性が予想以上に大人でよかったぞ!
下半身はもう準備を開始してるけどね!
「しんちゃんはネネのこと嫌い?
ネネの体じゃ満足できない?」
…勿論嫌いじゃないよ。
怖い面もあるけど、優しい面だってある。
頼りがいがあるし、女の子らしさだって持ち合わせてる。
日に日に可愛くなってくなーって思ってたし。
でもネネちゃんは今まで妹のようで、時にはお姉ちゃんのようで。
そんな風に見たことはなくて。
ネネちゃんの両頬に添えられたままの俺の手の上に、
ネネちゃんの手が添えられた。
そのまま俺の手は弛んで、ネネちゃんの顔は自由を取り戻した。
「ねえ、しんちゃん?
ネネの一生のお願い。
抱いて?」
その言葉と共に降ってきたのは、柔らかい唇。
侵入してきたのは、薄いけれどもしっかりと意志を持った舌。
絡めてしまったのは、己の儚い理性が崩れ去った証。
水を得た魚のように柔らかい肌を動き回るのは、箍が外れた少年の欲望。
抗うことができなかったのは、若さの所為にしたい。
あの時にちゃんと気付いていればよかった。
ネネちゃんの甘い罠に嵌ってしまったこと。
もう抜け出すことなんてできないこと。
その後。
同じ高校に入学してからも、何度も何度も体を重ねた。
断る理由はあったけど、甘い蜜の味を手放せなくなっていた。
彼女は本当に俺のことなんか気にせずに次々とオトコを作る。
俺がそれを見て何も思わないと思っているんだ。
こんな気持ちが、今更生まれてしまうだなんて。
性欲と愛情をごっちゃにしているって?
そんなことない。
純粋に俺は彼女を求めている。
若かりし日の過ちは、今でも僕の心を痛めつける。
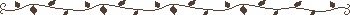
しんちゃんが大好きだから、付き合わないネネちゃんと
ネネちゃんに近付いていく度に、好きになってしまうしんちゃん。
ネネちゃんに先に予防線を張られてしまったので、今更想いを告げることもできず、
求められれば、いけないとは分かっていても拒否なんてできるわけもなく、
日々が過ぎる。
2人の「好き」の違いが、
体を重ねるごとに大きくなっていくことに気付いているのは、少年ばかりなり。
