「ヘタレ。」
ネネちゃんの口から出た言葉だった。
「え、何。久し振りにその単語聞いたんだけど ;
僕、何かしたっけ?」
真顔で、平気で彼氏にこんなこと言うのは、僕のお姫様。
この子が『姫』と言われる所以はその見た目からだけではない。
彼女の横暴ぶりも、堂々とした態度も、人に『姫』と言わせる。
でも、いきなり『ヘタレ。』だなんて…。
「最近全然言ってなかったから言ってみたの。」
そう言い放ったネネちゃんは、まだ無表情のままだった。
機嫌、悪いみたいだ。
僕の部屋で、ミルクティーを飲みながらテレビを見るネネちゃん。
うーん。確かに夕方のテレビ番組はつまらないけど…。
あったかいミルクティーはネネちゃんのお気に入りだ。
寒い冬、彼女の体を芯から温めてくれるもの。
ネネちゃんが何も言わなくても、寒い季節に僕の家に来たら必ずこれだと決まっている。
もしおいしくなかったら、僕が聞かなくても「やり直し」と言い放つから、ミルクティーに不満はないのだろうけど。
「映画でも見る?」
「いい。」
うーん。どうしたもんか。
「足、疲れた。」
「ん?はーい。じゃあこっちおいで。」
そっか。今日から体育の授業で持久走が始まったんだっけ。
テレビの方に向いていたネネちゃんの体は、僕の方を向き、足を投げ出した。
僕は膝の上にこの細い足を乗せて、優しくマッサージする。
「…。」
「ん?どうしたの?」
「なんか…マサオくん成長したよね。」
そう言って、ネネちゃんはミルクティーの入ったカップを見た。
「ネネがしてほしいこと、全部言わなくてもするようになったし、何事にも動じなくなった。」
ネネちゃんの為に、美味しいミルクティーの入れ方を調べた。
ネネちゃんが何も言わなくても、機嫌が分かるようになった。
ネネちゃんの一言だけで、僕にどうしてほしいのか気づけるようになった。
ネネちゃんになら何を言われようと平気だった。
だってその一言がネネちゃんのストレス解消であり、愛情表現であるのだから。
成長か。
確かに、小さい頃は全てに怯えていたっけ。
「はは。そりゃそーでしょ。ネネちゃんに何年鍛えられたと思ってるの?
5歳の頃からだから…。
わ!12年だって。ネネちゃん知ってた?」
「知ってるわよ、それくらい。」
鍛えられたと言えばそうなのだが、それだけではない。
ネネちゃんの本当の部分を知ることができたから、僕がネネちゃんに何をすべきなのか見出せた。
だって、他の奴らには愛想笑いとかしてるけど、僕たち防衛隊の皆にはちゃんと本当のネネちゃんを見せてくれる。
いっぱい毒を吐いて、すっきりした顔になる。
そんなネネちゃんを見ると安心するんだ。
可愛いだけのネネちゃんなんて、ネネちゃんじゃないから。
「いやーでも、僕の成長もネネちゃんに認められつつあるってことだね。」
そんなこと言うと、ネネちゃんは頬を膨らまして、ぶーたれた顔になる。
「やだ。成長なんかしなきゃよかったのに。」
「えー。なんで?格好良くなったってこの間褒めてくれたじゃん。」
げしっ。
ネネちゃんはマッサージをされていた足で、僕のお腹を蹴った。
調子に乗るなってことですね。
「余裕のあるマサオくんなんてマサオくんじゃないもん!」
「はは。でもほら、僕たちネネちゃんのおかげで寛大な心になったよ。
今ならどんなネネちゃんでも受け止めることができる。」
僕は大人になって良かったと思ってる。
大人になって、ネネちゃんのことが段々と分かるようになってきたから。
キツイこと言ってるけど、そんな言い方できるのも、こんな悪態を晒せるのも僕たちにだけなんだって知った。
本当のネネちゃんを見ることが許されてるのは僕たちだけなんだ。
だから僕には、怖いものはないと思える。
そんなことを思っていたら、ネネちゃんは言うんだ。
「…何よ。『たち』って。ネネを受け止めるのはマサオくんだけで充分でしょ。」
って。
言った後に触れたネネちゃんの唇。
『そうだね。』
って、僕なりの答え伝わったかな。
辛くなったら僕を呼んで。
ネネちゃんの中に潜む毒を、すべて取り除いてあげるから。
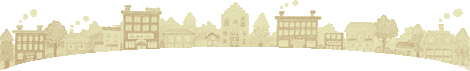
ドSネネちゃんと、ドMマサオくんを書きたかった。
まず一言目に「ヘタレ。」と姫に言い放ってほしかった。
そしたらなんか。
Mではなくなってしまいました。
だってマサオくん余裕ありすぎて、いじめにくくなってしまったんだもん(;_;)
表面上はネネマサに見せかけて、やっぱり本質の部分はマサネネ★
ネネちゃんは無意味にドSをしているのではないと。
マサオくんは無意味にドMをしているのではないと。
そんな感じが少しでも伝わっていただけたら幸いです。
なんかすごい好きなように書いてます。
バカっぽくてくだらないです。
お目汚しです。
はい。